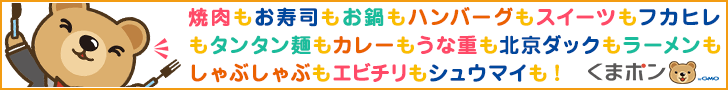
2017年に日特の巻き線機を更新した。
その時巻き斑が出来てボビンの向きを変えた効果が大きかったという事があった。
実は同型のじ巻き線機を使う製品がもう一つあり、今回はそちらで同じような現象に対応した。
巻き線機は同型で、同じくカンタル線によるヒーター巻き線である。
線径はちょっと細くてφ0.3、テンション装置も一回りちいさいTCLを使っている。
巻くのはガラス管種類、外径φ22とφ18になる。
ピッチは細かい部分では P=0.45、何と隙間が線径の半分しかない。
それでも今まで何の問題も無く巻けていたのだった。
異変が起きたのはボビンの荷姿が変わったこと。ボビンは4㎏巻きらしいのだが、我が社の発注単位は1㎏だったので、商社にて小分けされていたらしく、若干寸法が異なっていた。以前にも同じことがありアダプタで対応していたが紛失、今回改めて作り直した。

で、ボビンを変えたら突然巻き斑が発生した。
どうもボビンから小分けする巻取りで線に撚れが入ってしまったらしい。
ボビンを縦置きにするか横置きにするかで斑の出方が変わる事が判っているのでまずはボビンの小分けをやめるべく発注単位も変更する事にした。
で、いくつかボビンが変わった訳だが、テンション設定を変えざるを得ず、最適値を探るのに苦労した。
そもそもマグネットワイヤーなどの銅素線はメーカー推奨の巻きテンション値があるのだが、カンタル線には無いので、巻き斑が無い、つまりピッチ0.45で隣の線との接触が無い事と、巻き線が緩まないこととした。緩まない事は巻き線後に超音波洗浄して線が動いていない事で確認した。
結局のところテンションとバックテンションの組み合わせの良いものを探すと言った地道な作業で何とか安定した組み合わせを見つける事ができた。
ノズルはガラスの回転に対して定められたピッチで動き螺旋状に線を引っ張るのだが、ガラス管に巻き付く位置が定まらない状態になる。図に示すように理想的な位置より、遅れるか揃うかである。ずれるきっかけは線の張力の変化と考えられ、緩むと遅れが生ずると考えられる。いくら張力が強くとも 先行する事はあり得ないので、許される範囲で強ければ良いと思うのだが、強すぎてもよろしくない。テンション装置の構造にもよるのだが、その時のあらゆる条件のバランスするところがあるのだろう。
結局のところ、何故斑が出来るのかという原因はよく分からない。
この項完 2021.7.3
戻る
